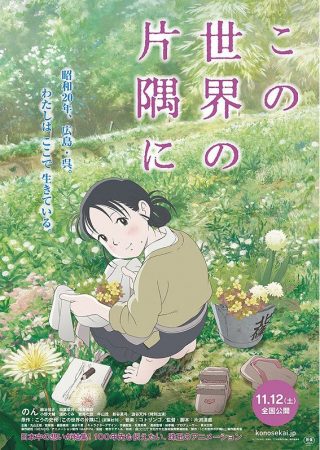オフィシャルサイトより加工転載
オフィシャルサイトより加工転載
沈黙 サイレンス ※ネタバレあるかも・・・
かなりヒットしているようです。
2週間ほど前に観ました。
その前に公開されると聞き、原作小説を読んでみました。
私の中学時代には、「どくとるマンボウ」派と「狐狸庵先生」派がいたように思います。
といっても、北杜夫については、中学生時分なので「白きたおやかな峰」や「楡家の人びと」などの純文学は手が届きませんでした。
読んでいたのは、もっぱらどくとるマンボウシリーズその他の滑稽小説。
狐狸庵先生・遠藤周作はネスカフェのCMの印象しかなく、映画化された「海と毒薬」などは気になっていたのですが、全く未読の状態でした。
で、今回始めて狐狸庵先生ではない、遠藤周作の代表作とも言うべき「沈黙」を読んで、打ちのめされたわけです。
はい、こんなに凄い小説家だったんだ。
隠れキリシタンへの迫害については、「青い空」などその他の作品に多数出てきます。
胸のムカつく所業の数々。
為政者にとって、「宗教」は諸刃の剣。コントロール不可能に陥れば、己と己の築きあるいは護るべき既得権が脅かされる存在です。
それは分かるのですが、ローマ皇帝ネロの時代から、なぜここまでキリスト教のみが迫害されるのでしょうか。迫害体質?
キリスト教同志の内紛もありましたが。
大体日本人の宗教観はファジーです。
神と仏をごちゃ混ぜにして、怪しまない。適当。
だからそれほど問題も起きない。
坊主がキャバクラに行っていようと、あまり咎める人もいない。
そこに一神教たる(シャレの通じない)キリスト教が入ってきたもんだから、当然のごとく排斥されるわけです。
この物語の舞台は長崎県。そして五島列島。
行ったことないけど、キリスト教徒の多い土地柄みたいですね。
寅さんが五島に行ったときも、教会が出てきたし。
この映画は原作を読んでから観たほうがいいやつだと思いました。
結構小説を忠実に再現しており、緻密な臭うような描写の原作を体験した方が映画がわかりやすいと思います。
迫害されて食うや食わずの日本人キリシタンは、メイクなどでリアルに汚している部分は多いのですが、なかでも凄いのが塚本晋也の大減量。
アメリカで栄養士についてもらって痩せたそうです。
監督の副業かとも思っていた塚本晋也ですが、俳優としても命削って挑んでます。
映画に掛ける情熱を考えればそれもむべなるかな。
最近、「シンゴジラ」といい、俳優として大活躍ですね。
主役はスパイダーマンのピーター・パーカーを演じたアンドリュー・ガーフィールド。マッチョじゃない派のハリウッドスター。
キーパーソンだけど、あまり出番のないのがリーアム・ニーソン。長い間日本にいて日本名もあるのに、日本語のセリフは一切なしというのもどうなのか。
ほぼ主役に近いポジションにキチジローという貧しい漁師(?)がいます。転びまくっている信者で、演じるのは窪塚洋介。
存在としては、鬼太郎のねずみ男にそっくりです。
原作を読んだイメージとしては、キチジローはもっと貧相で小柄なブ男かと思っていたので、窪塚洋介ってどうよと思ったのですが案外はまっていました。
一瞬しか映らない中村嘉葎雄。エンドロールでやっぱりそうだったかと確認。
それいるか?という帝王・高山善廣。
中村嘉葎雄にセリフがなく、一言だけとは言えセリフのあった高山。
しっかりとした俳優にはセリフがなくても演技をまかせられるということでしょうか。
当然ちゃあ当然なのですが、ヘンな日本描写はない。日本人スタッフの頑張りもすごい。
一箇所だけ気になったシーン。
ハリウッド映画で剣(特に日本刀)を鞘から抜く時。
刀同志を合わせる時はともかく、抜刀・納刀の際にも”シュリーン”という効果音が入ります。
明らかに金属同士がこすれる音。鞘は木製なので、そんな音がなるのはおかしい。
というか、多分無音でしょう。
どうしても効果音を入れたいのでしょうね。一箇所そんなシーンがありました。
・・・よ、マーティン。
アメリカも日本も出演俳優が凄く良いです。
二時間半、まったくダレずに観ることができました。
★★★★★