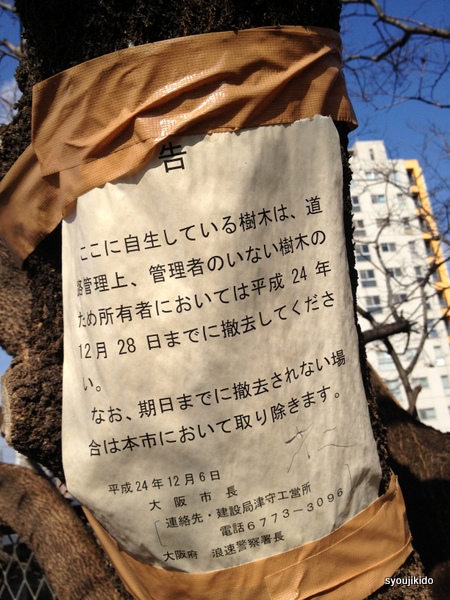最近はテレビのゴールデンからも消えて久しく、youtubeでみるくらいしかしていないプロレス。
ボクの最古のプロレスの記憶は・・・
日本プロレスのテレビ中継。
ブルート・バーナード、スカルマーフィ組対吉村道明、アントニオ猪木組だと思う。
薄ぼんやりとした記憶なので、バーナード以外は合ってるか自信はない。
試合は乱戦の中、間違ってブルートがマーフィをスリーパーにとらえて夢中で締め上げる。
と、途中でその禿頭(マーフィは全身無毛の怪奇レスラー、バーナードもスキンヘッド。ツルピカコンビ)の手触り・・・ツルツルの撫で上げ感で、オーバーに間違いに気付いてオノレのアタマを抱えるブルート。
マーフィは怒ってやり返すでもなく、腕を組んで膨れて戦いをボイコット。
会場は爆笑の渦と・・・。そのあたりが抜群にうまい!
ほとんど大阪プロレスの世界。
こんなのからプロレスファンになったんだから、ちょっとやそっとでは見捨てないよー( ゚∀゚ )
で、それ以前の大スターとして、ネームバリュー抜群なのが、このフレッド・ブラッシー。
今は極端にグロい路線に走っているプロレスもあるが、あれは頂けない。
プロレスの中の反則攻撃ではなく、プロレスの体裁を借りた残酷ショーだ。
これだけHIVや感染症の危険性が言われているのに、大丈夫なんでしょうかねぇ。
それはともかく、ブラッシーの噛みつき攻撃(もちろん反則ですが)って、冷静に考えるとすごいことですね。
相手に噛み付いて大流血させるなんて。
もっとも、本当に皮膚を噛み破ってるわけではないでしょうが。
まだ力道山の頃はプロレスがかなり純粋な競技であるという大方の認識だったわけで。
力道山のプロモーターとしての判断もかなりバクチだったんじゃないでしょうか。
このクラッシー・フレディー・ブラッシーというのは、ボクもリアルに知っているわけではなく、すでに、マネージャーに転身して、猪木vsアリ戦の時にアリ側についていた元レスラーでした。
あと、奥さんが日本人で、実は親日家だということ。
そして何よりもヒールではあるが、プロ中のプロであるという評判。
力道山が非業の死を遂げた時にも、哀悼の意を表さず「地獄で待ってろ!」と言い放ち、あまつさえ力道山は地獄ではなく天国にいますと言ったインタビュアーに、さらに「いや、奴は俺と同じ地獄行きさ!」と言い返したとか。もちろん馬鹿なんじゃなくて、その時の日本における力道山の重要性も十分に認識した上で、徹底的にヒールを演じたということ…は聞いていた。
客の比較的おとなしい日本だけでそうなのではなく、本書によるとやはりヒートアップしたアメリカの観客に刺されたりなどということは日常茶飯事だったらしい。
投げつけられた卵のせいで、実は片目は殆ど失明状態でもあったとのこと。
今ではさすがにないだろうが、ブラッシーより何世代も後のテリーゴディ辺りもカーニバルレスラーだったらしい。
そしてブラッシーもアスリートとは程遠い、そのような見世物小屋的な世界からの叩き上げだ。
本書はその辺りも詳細にしかしコンパクトにまとめ上げている。
しかも、ブラッシーはアメリカ人レスラーの中にあってはかなり小兵の部類に入る。
にもかかわらず、錚々たるシューターの名前も多く出てくるし、十分に渡り合ったのだろう。
自分以前に全米レスラーのアイコンであり、自分もその路線にあることを認めているゴージャス•ジョージを最大限に讃えてはいるが、ご存知の通りジョージには人間力ともいうべきものが大きく欠落しており、カール•ゴッチ、ビル•ミラーのセメントブラザーズにボコボコにしばかれてしまったりしている。
その点、ブラッシーは最終章のビンス•マクマホンの言葉によると、マクマホン•シニアからビンスがWWFの全権を移譲する際の条件の一つとして、クラッシー・フレディー・ブラッシーを生涯雇用し「ファイトマネー」を支払い続ける、というものだったらしい。
それほどWWFとアメリカプロレス界に大きな功績を残したということか。
あまり親しくはしたくないな〜というようなエピソードも多々あるのだが。
このちょっといい話的なオチの付け方が良い一冊ではあります。
本書のタイトルは、本場では有名なブラッシーの決まり文句です。