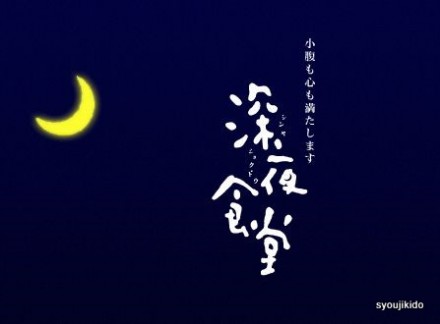
昨年末からTV放送されていたドラマ「深夜食堂2」。
TVドラマをみなくなって何十年か経つが、二年ほど前にシリーズが始まって、はまってしまったドラマでした。
それから原作を揃え、遅々として進まない新刊のリリースを心待ちにしている漫画です。
ドラマのシリーズ1が10作品。今回のシリーズ2も10作品の合計20話です。
前シリーズは全部見られなかったこともあり、DVDボックスを予約で購入。ヘビロテしております。
嫌が上にも高まるシリーズ2への期待。
我が家のHDレコーダは地デジ化と同時に引退。友人に撮ってもらって、年明けと同時に鑑賞開始。昨夜、やっと全話終了しました。
見終わっての感想を一言で表すと「換骨奪胎」。京都の清水寺まで行って墨書したくなるな。
このシリーズは劇場映画の監督が撮るということが又、ウリで、劇場版並の作品レベルとか、訳の解らんというか、失礼な表現がなされています。
セットの完成度や空気感なんかは、確かにそういう表現もわからなくはない。
さて、この「換骨奪胎」ですが。
必ずしもネガティブな表現ではなく、それこそ劇場映画でも良くみられます。
先日公開の「ワイルド7」なんかも観てないけど、おそらくそうでしょう。ハリウッド映画でも散見される。
フォーマットだけなぞって、あとは時代に即するなどの理由でオリジナルな作品にしてしまう。
現在の仮面ライダーなんか、あきらかにそうですね。
問題はそれで成功するか否かということですが。
今回の「2」は残念ながら『否』かなあ・・・。
東日本大震災の影響が随所に見られ、メモリアル的な要素もあることはわかります。
しかし、原作の持つ日常性(ゆるいリアリティ)やドライとウェットがないまぜになった明るいポジティブな諦念というか閉塞感のようなものが・・・ない。
基本的に原作に則った何話かはイイカンジなんですが、最終話とかそれはないやろうという感じ。
オダギリジョーは好きだし良いんだが、他のドラマでやってくれよというか。
メイン監督の松岡錠司さんがインタビューで言ってました。
「フレンチ・コネクションの1と2は拮抗している。違う切り口をぶつけて、前作に遜色のないものにしている。ゴッドファーザーのシリーズもそう。」
いや、まさにそのとおりなんですが、ちょっと冒険しすぎじゃないかな。
観客を置いて行くのも全然問題ないですが、今回は大上段の空振りみたいな気がする。
シリーズ2は・・・DVD購入は見送るかな。少し考えます。




